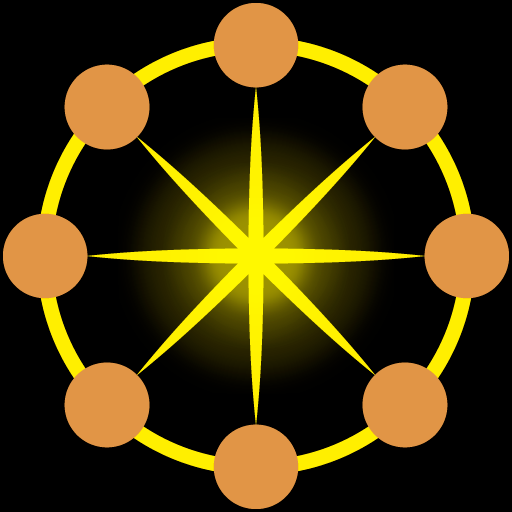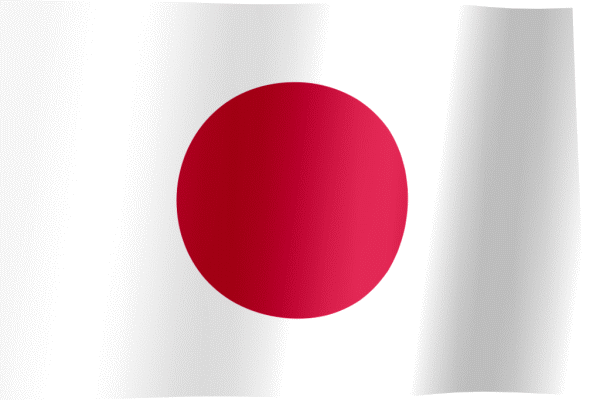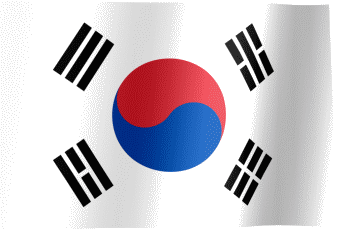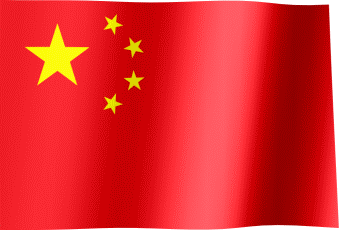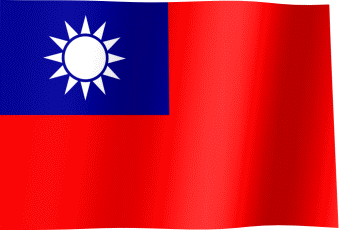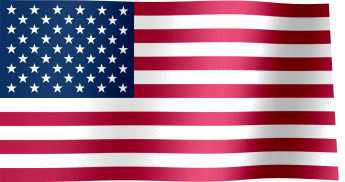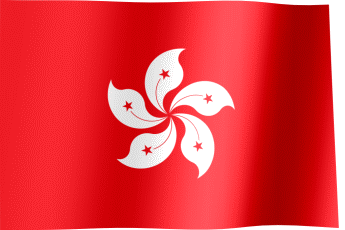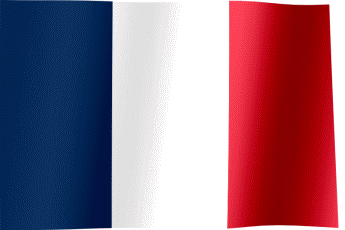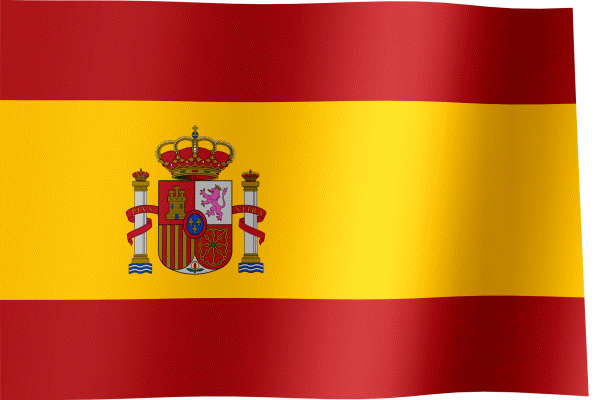日本創世の秘密「古代神話と歴史の真実を解き明かす」

日本創世の秘密・番外編「隠された歴史と神話の謎に迫る」
序文
神々の物語には、語られるものと、語られなかったものがある。
『日本創世の秘密』では、日本神話の中心となる物語を紐解いてきました。しかし、日本神話の中には、公式な記録にはほとんど残らず、歴史の影に埋もれてしまった「封印された神々の伝説」が数多く存在します。
- なぜ月読命の神話は語られなくなったのか?
- 神武天皇が即位する前に統治していた「もう一人の天孫」とは?
- 大国主命は本当に国を譲ったのか?
- 黄泉の国や天の浮橋——神々と人間の世界の境界はどこにあるのか?
本書『日本創世の秘密・番外編』では、これらの謎を追い、日本各地に残る伝承や神話の痕跡を辿ります。そして、神話がどのように形成され、どのように歴史と結びついていったのかを探求していきます。
日本神話は、決して過去の物語ではありません。それは今もなお、日本という国の精神や文化に深く根付いています。
この本を通じて、神々の遺した「もう一つの物語」に触れ、日本神話の新たな側面を発見していただければ幸いです。
それでは、神々の影を追う旅へ出かけましょう。

第一話 隠された神々—歴史に埋もれた存在たち
日本神話には、よく知られた神々とは別に、ほとんど語られることのない「隠された神々」が存在します。
これらの神々は、なぜ神話から消えてしまったのか?
彼らの存在は、何を意味していたのか?
本編では語られなかった、日本神話の深層に迫ります。
1. 天香山命(あめのかぐやまのみこと)
忘れられた「第四の貴神」
日本神話では、天照大神・月読命・須佐之男命の三柱の神が「三貴神(さんきしん)」として有名です。
しかし、古い伝承には「もう一柱の神」がいたとされています。その神の名が天香山命(あめのかぐやまのみこと)です。
天香山命は、かつて天照大神と共に高天原を治めていた神であり、天孫降臨の際にも重要な役割を果たしたとされます。しかし、『古事記』『日本書紀』では、ほとんど触れられていません。
なぜ彼の存在は消えたのか?
- 太陽神信仰を強調するため、天照大神の存在を際立たせる必要があった。
- 天香山命の役割が、後に別の神(猿田彦神や瓊瓊杵尊)に置き換えられた。
- 大和朝廷が統一を進める過程で、異なる地域の神話が整理され、影が薄くなった。
もしかすると、天香山命は「天照大神の対等な存在」だったのかもしれません。しかし、その存在が薄れたことで、今の日本神話の構造が形作られたのです。
2. 級長津彦命(しなつひこのみこと)
風を司る謎の神
日本には、風の神が存在します。それが級長津彦命(しなつひこのみこと)とその妻級長戸辺命(しなとべのみこと)です。
彼らは、日本神話の中でほんの一瞬だけ登場しますが、その後の物語ではほとんど触れられません。
なぜなのか?
- 風の神としての役割が、後に須佐之男命の「嵐の神」として統合された。
- 風という不可視の存在が、信仰の対象として確立しにくかった。
- 外来の神々(仏教の影響など)が入ってくる過程で、重要性が薄れた。
しかし、風の神は海洋国家である日本にとって極めて重要な神だったはずです。風を制する者が航海を制し、国を繁栄させる。にもかかわらず、級長津彦命は歴史の影に埋もれてしまいました。
このことは、日本神話がどのように整理され、形作られたのかを示す重要な証拠かもしれません。
3. 角杙神(つぬぐいのかみ)と活杙神(いくぐいのかみ)
国造りの神々
イザナギとイザナミが国造りを始めた際、最初に生まれた神々の中に「角杙神(つぬぐいのかみ)」と「活杙神(いくぐいのかみ)」がいます。
しかし、彼らの名前はほとんど知られていません。
- 角杙神は「土地の杭を打つ神」
- 活杙神は「土地を活性化させる神」
つまり、彼らは「国を作る土台」となる神だったのです。しかし、その後の日本神話ではほとんど登場せず、国造りの中心はイザナギ・イザナミへと集約されていきます。
これは、日本の統治体系が発展する中で、神話がよりシンプルに整理され、主要な神々に焦点が絞られた結果だと考えられます。
4. 邪神の存在—日本神話から消された「敵」
日本神話には、「邪神」とされる存在がほとんど登場しません。これは他の神話(ギリシャ神話のハデスや北欧神話のロキなど)と比べると不自然です。
しかし、実は古い伝承には「敵」として描かれた神々がいた可能性があります。
星の神「天津甕星(あまつみかぼし)」
- 神武天皇の東征の際、天照大神に反抗した存在とされる。
鬼や魔神の原型とされる神々
- 地方に伝わる民間伝承には「鬼」として残った古い神々が存在する。
須佐之男命の影の存在
- 彼は「荒ぶる神」として描かれるが、本来はもっと大きな対立を生んでいた可能性がある。
星の神「天津甕星(あまつみかぼし)」
- 神武天皇の東征の際、天照大神に反抗した存在とされる。
鬼や魔神の原型とされる神々
- 地方に伝わる民間伝承には「鬼」として残った古い神々が存在する。
須佐之男命の影の存在
- 彼は「荒ぶる神」として描かれるが、本来はもっと大きな対立を生んでいた可能性がある。
これらの神々は、後の時代に整理され、「敵ではなく、神々の一部」として神話が編纂された結果、ほとんど語られなくなったのかもしれません。
日本神話の深層
私たちが知るべきこと
ここまでの話を通じて、日本神話には「表に出てこない神々」が多く存在することが分かります。
なぜ彼らの存在は消されたのか?
それは、日本という国が発展する過程で、神話が統一されていったからです。
- 太陽信仰を中心に据えるために、月読命が影を薄くされた。
- 支配者の正統性を示すために、饒速日命の存在が消された。
- 神々の戦いを強調せず、調和の物語にするために「邪神」が抹消された。
しかし、それでも彼らの痕跡は、日本各地の神社や民間伝承の中に残っています。

第二話 神々の影 — 封印された神社と伝承
日本各地に残る「隠された神々の痕跡」
日本神話の中で語られなくなった神々。しかし、彼らは完全に消えたわけではありません。実は、日本各地には今も彼らを祀る神社があり、古い伝承としてその存在が密かに受け継がれています。
今回は、「封印された神々の神社と伝承」を探る旅へ出ましょう。
1. 天津甕星神社(あまつみかぼし)
封印された「星の神」
天津甕星(あまつみかぼし)とは?
天津甕星は、「星の神」として伝わる神ですが、日本神話では「反逆の神」として描かれることが多い存在です。
神武天皇が大和の国を統一する際、この神は天照大神の意志に背き、最後まで抵抗したとされています。そのため、後の時代には「祀ることを禁じられた神」とも言われています。
神社の痕跡
- 茨城県の鹿島神宮の奥宮
- 栃木県の星宮神社(ほしのみやじんじゃ)
- 群馬県の貫前神社(ぬきさきじんじゃ)
これらの神社には、天津甕星を祀るとされる伝承が残されています。特に「星宮神社」は全国に点在し、古代の星信仰と結びついています。
もしかすると、天津甕星は「単なる反逆の神」ではなく、古代日本における「星を司る重要な神」だったのかもしれません。しかし、その存在は天照大神を中心とする神話体系の中で影を薄められたのです。
2. 物部神社(もののべじんじゃ)
饒速日命の消えた歴史
饒速日命(にぎはやひのみこと)の正体
前回の話でも触れたように、饒速日命は神武天皇が到来する前に大和を統治していた王であり、「もう一人の天孫」として伝わる神です。
しかし、彼の系譜は日本神話の中でほとんど語られず、神武天皇の即位とともに歴史から消えていきました。
彼を祀る神社
- 奈良県:物部神社
- 大阪府:磐船神社(いわふねじんじゃ)
- 鳥取県:宇倍神社(うべじんじゃ)
これらの神社には、「饒速日命は天の船に乗って降臨した」という伝承が残されています。磐船神社には巨大な岩の船があり、「天孫降臨」のもう一つの伝説が息づいているのです。
もし饒速日命の伝説が語られ続けていたら、神武天皇とは異なる「もう一つの王統」が成立していたかもしれません。しかし、それは歴史の中で封印され、現在の神話の形に整理されてしまいました。
3. 鬼伝説と神話の関係
消された「鬼の神」
鬼とは何か?
日本各地に伝わる「鬼」の伝説。彼らはしばしば「恐ろしい存在」として語られますが、実は古代の神々の名残である可能性があります。
- 大和の「長髄彦」:鬼の祖とされる存在。
- 出雲の「八岐大蛇:須佐之男命に敗れた異界の神。
- 東北地方の「アラハバキ神」: 征服された土着神として封印された。
これらの神々は、後の時代に「鬼」として伝承され、恐れられる存在になっていきました。
鬼の神を祀る神社
- 栃木県:星宮神社(天津甕星との関連)
- 島根県:八重垣神社(八岐大蛇の伝説)
- 青森県:荒覇吐神社(アラハバキ神を祀る)
これらの神々は、古代日本における「異なる信仰の象徴」だったのではないでしょうか。しかし、中央の神話体系の中で「鬼=異端」として扱われ、封印される運命をたどったのかもしれません。
4. 出雲の謎
なぜ大国主命は「隠れた神」になったのか?
出雲の国を治めていた大国主命(おおくにぬしのみこと)は、天照大神の使者に国を譲ったとされています。
しかし、本当に彼は「国を譲った」のか?
- 出雲大社の社殿の構造:通常の神社とは異なる、異質な形式。
- 「見えない神」としての信仰:出雲では、大国主命の神像は存在しない。
- 出雲神話と大和神話の対立:古代の支配構造の名残?
大国主命は、本来ならば「日本の統治者」として崇められてもおかしくない神でした。しかし、「国譲り」の神話によって、彼は「隠れた神」となり、出雲の地に留まることになったのです。
これは、日本神話が編纂された際、大和朝廷の支配を正当化するために出雲神話が書き換えられた可能性を示しています。
まとめ
神々の影をたどる旅へ
今回紹介したように、日本各地には「隠された神々」を祀る神社が数多く存在します。
「神話の影」を追うことは、日本のルーツを知ることに繋がる。
封印された神々の物語を辿ることで、日本神話がどのように形作られたのか、そしてその背後にどんな歴史が隠されているのかを探ることができるのです。

霊蹟天岩戸(あまのいわと)を斎ひ奉る天岩戸神社
第三話 異界と日本神話 — 神々が交わる境界線
日本神話では、神々の世界と人間の世界が交わる「境界」がたびたび登場します。
- イザナギが黄泉の国を訪れた「黄泉比良坂(よもつひらさか)」
- 天照大神が隠れた「天岩戸(あまのいわと)」
- 天と地を結ぶ「天の浮橋(あめのうきはし)」
- 鬼や異形の者が住むとされる「鬼門(きもん)」
これらの場所は、単なる神話の舞台ではなく、今も日本各地に「異界との境界」として伝承が残っています。
今回は、「神々の世界と人間の世界の境界線」をテーマに、その謎に迫ります。
1. 黄泉比良坂
冥界への入り口
黄泉比良坂(よもつひらさか)は、イザナギが黄泉の国へと降り、そして戻ってきた場所とされています。
この神話は、日本神話の中でも特に重要な「死と再生の物語」となっています。
生者と死者の世界を分ける境界線
- 「見るな」という禁忌が存在する(イザナギはイザナミの姿を見てしまい、逃げることになる)
- 大きな岩(黄泉戸塞)によって封印される(この封印が、後の鬼門の概念につながる)
現在の「黄泉比良坂」
現在、黄泉比良坂の伝承が残る場所は、島根県松江市の東出雲町にある「黄泉平坂(よもつひらさか)」です。
そこには大きな石が並ぶ道があり、今も「ここを超えてはならない」という伝承が残っています。
もしかすると、古代の日本人は「死者の世界と生者の世界は交わるべきではない」という考えを持っており、それを神話として語り継いできたのかもしれません。
2. 天の浮橋
神々が降り立つ場所
天の浮橋(あめのうきはし)は、「天と地を結ぶ橋」として日本神話に登場します。
- イザナギとイザナミが、ここから天沼矛(あめのぬぼこ)を垂らして国造りを始めた。
- 天孫降臨の際、瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)はここを通って地上へ降りた。
天の浮橋の場所
- 鹿児島県霧島市の「高千穂峰(たかちほのみね)」
- 宮崎県西臼杵郡の「天安河原(あまのやすかわら)」
これらの地には、「天の世界と地上の境界」としての伝承が残っており、特に高千穂峰は「天孫降臨の地」として今も信仰を集めています。
この神話が示すのは、「天と地は繋がっている」という考え方です。つまり、神々の世界は遠い存在ではなく、ごく近くにあり、時には人間と交わるものとして描かれていたのです。
3. 天岩戸
神が隠れる場所
天岩戸(あまのいわと)は、天照大神が須佐之男命の暴れぶりを嘆き、隠れてしまった洞窟です。
- 天照大神が隠れると、世界は闇に包まれた。
- 神々が「天の岩戸開き」の儀式を行い、彼女を引き出した。
現在の「天岩戸」
- 宮崎県高千穂町の「天岩戸神社」
- 三重県伊勢市の「伊勢神宮内宮」(別説ではここが天岩戸の地とされる)
天岩戸神話は、「太陽の神がいなくなると、世界が闇に閉ざされる」という、日本人の太陽信仰を象徴する話でもあります。
また、「神が隠れる=力を失う」という考え方は、後の時代にも繋がり、「封印された神々」の伝説の原型になったのかもしれません。
鬼門
異界への入り口
鬼門(きもん)とは、日本の陰陽道で「鬼が出入りする方角」とされるものです。
- 鬼門は「北東(艮・うしとら)」の方角にある。
- 裏鬼門は「南西(坤・ひつじさる)」の方角にある。
この考え方は、風水や陰陽道と深く関わっていますが、元をたどると「異界との境界線を定める」日本古来の信仰が影響しているとも言われています。
鬼門の象徴的な場所
京都御所の「猿ヶ辻(さるがつじ)」
- 京都御所の北東にある場所。鬼門封じとして、ここに猿の像が置かれている。
比叡山延暦寺
- 京都の鬼門に位置し、都を守るための霊的な結界として建立された。
成田山新勝寺・高尾山薬王院
- 江戸幕府が「鬼門封じ」のために祀った寺院。
鬼門の考え方は、「鬼が出入りする=異界が開く」という概念であり、これは黄泉比良坂や天岩戸の話と共通しています。
つまり、古代の日本人は「この世界には、人間の世界と神々・異界の世界を繋ぐ境界がある」と考えていたのです。
まとめ
神話の境界は今も存在する
今回紹介したように、日本には「神々の世界と人間の世界の境界」が至るところに存在しています。
- 黄泉比良坂:死者の世界への入り口
- 天の浮橋:天と地を繋ぐ道
- 天岩戸:神の力が封じられる場所
- 鬼門:異界が開く方角
これらの伝説は、単なる昔話ではなく、今も日本各地にその「痕跡」が残っているのです。

第四話 神々と人間の契約 — 神話が示す未来
神々と人間はどのように関わってきたのか?
日本神話には、「神々と人間が結ぶ契約」がたびたび登場します。
- 天孫降臨:天照大神が瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)に「葦原中国(地上世界)を治めよ」と命じた。
- 国譲り:大国主命が「天の神々の意志」に従い、出雲を譲った。
- 三種の神器の継承:天皇が神器を受け継ぎ、天の神々の意志を継ぐ存在となる。
これらの神話は、「日本という国が神々と結んだ契約のもとに成り立っている」という思想を根底に持っています。
では、この契約は未来にどう影響するのか?
今回は、「神々と人間の契約が示す日本の未来」に迫ります。
1.天皇の「神の子孫」という思想は未来にどう影響するのか?
天皇と神々の契約
日本神話では、「天皇は天照大神の直系の子孫」とされています。これは「天孫降臨」の神話によるもので、瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)が地上に降り、やがて神武天皇へと繋がることで、天皇の血統は神々の意志を継ぐものとされているのです。
この考え方は、古代だけでなく、現代の天皇家の存在意義にも関わっています。
- 伊勢神宮の祭祀は、天皇が直接関与する(神々との繋がりの維持)
- 三種の神器は、天皇即位の儀式に欠かせない(神器の継承=神の意志の継承)
- 「万世一系(ばんせいいっけい)」の思想は、神話の延長線上にある(皇統の正当性)
つまり、日本という国の根幹には「神々と天皇が結んだ契約」が存在しているのです。
しかし、この契約は未来においても維持されるのか?
- 現代では「天皇の役割とは何か?」が議論されることが増えている。
- 神話的な正統性が未来の日本社会でどのように受け継がれるのかは未知数。
つまり、「神々と天皇の契約」は今後どのように解釈されるのかが、日本の未来に影響を与える可能性があるのです。
2.「神々が見守る国」としての日本の意味とは?
日本には「八百万の神(やおよろずのかみ)」という考え方があります。
これは、「この世界のあらゆるものに神が宿る」という思想であり、自然崇拝やアニミズム的な信仰と深く結びついています。
神々が見守る国=自然と共に生きる国
- 山の神、海の神、田の神など、自然そのものが神とされる。
- 神社の多くは「自然の中に建てられる」(例:伊勢神宮、出雲大社)
- 祭りや伝統行事は「神々への感謝」を込めたものが多い。
この考え方は、未来の日本にどのような影響を与えるのか?
未来への示唆
環境保護の視点
- 「自然を神聖視する思想」は、持続可能な社会のモデルとなる可能性がある。
- 気候変動や災害と向き合う際、「自然との共生」という考え方が重要になる。
精神文化の継承
- 科学技術が発達しても、人々が精神的な拠り所を求める限り、「神々の見守る国」という思想は生き続ける可能性がある。
つまり、日本の神々の信仰は、未来においても「人と自然の関係を見直すための鍵」となるかもしれないのです。
3. 神話が示す「日本の未来」とは?
日本神話には、「世界は常に変化し、神々の意志を継ぐ者がそれを導く」というメッセージが込められています。
例えば
神武東征と開拓精神
- 日本神話では、神武天皇は困難を乗り越えて新しい国を築いた。
- これは「挑戦と開拓の精神」を象徴しており、未来の日本にも通じる価値観である。
天岩戸の神話と「復活」の概念
- 天照大神が隠れ、世界が暗闇に包まれたが、再び光を取り戻した。
- これは、「困難な時代の後には、必ず新たな光が生まれる」という希望の象徴とも解釈できる。
- 現代の日本社会が直面する課題(少子高齢化、経済問題など)にも、この神話の教訓が活かせるかもしれない。
国譲りと「共存」の考え方
- 大国主命は、武力ではなく交渉によって国を譲った。
- これは「支配ではなく共存による統治」という考え方を示している。
- 未来の国際社会において、日本が「共存と調和」の価値観を発信していく役割を担う可能性がある。
まとめ
神話は未来へと続く物語
日本神話は、過去の物語ではなく、未来を示唆するメッセージが込められた物語でもあります。
- 天皇の存在: 日本のアイデンティティの象徴として、どのように未来に受け継がれるのか?
- 八百万の神の思想: 環境問題や精神文化の継承にどう影響を与えるのか?
- 神話の教訓: 挑戦、復活、共存という価値観が、未来の社会にどう生かされるのか?
これらのテーマは、私たちが「日本という国の未来をどう考えるか?」という問いに繋がっています。
つまり、日本神話は「過去の起源を語る物語」であると同時に、「未来への指針を示す物語」でもあるのです。
エンディング
「日本創世の秘密」とは何だったのか?
このシリーズを通じて、日本神話が単なる昔話ではなく、日本の文化や精神に深く根付いた存在であることを描いてきました。
そして、その物語は、今もなお続いています。
「神々の物語は、未来を照らす光となるかもしれない。」
そう考えたとき、日本神話の持つ本当の意味が見えてくるのではないでしょうか。
「日本創世の秘密・番外編「隠された歴史と神話の謎に迫る」完結

第五話 日本神話をもっと深く知るために — 資料と学び方
日本神話の物語を読んで、「もっと詳しく知りたい」と思った方のために、今回は「日本神話を学ぶための資料や方法」を紹介します。
古事記や日本書紀はもちろんのこと、神話を体感する方法や、世界神話との比較まで、多角的に日本神話を学ぶ方法を探っていきます。
1.日本神話の基礎を学ぶ—必読の古典
① 古事記(こじき)— 最古の神話書
成立:712年(奈良時代)/編纂者:太安万侶(おおのやすまろ)
特徴
- 日本最古の歴史書であり、主に「神々の物語」が中心。
- 口承で語られていた神話を文字に残したもの。
- 文学的な表現が多く、神々のエピソードが生き生きと描かれる。
おすすめの現代語訳
- 『現代語 古事記』(角川ソフィア文庫): 読みやすい現代語訳で、日本神話の入門書として最適。
- 『口語訳 古事記』(福永武彦 訳): 詩的な表現が特徴的で、日本神話の世界観を美しく再現。
② 日本書紀(にほんしょき)— 公式の歴史書
成立:720年(奈良時代)/編纂者:舎人親王(とねりしんのう)
特徴
- 天皇の正統性を示すために書かれた「公式の歴史書」。
- 日本神話の他に、中国や朝鮮の歴史も参考にしながら記述。
- 「異伝(いでん)」と呼ばれる複数の異なる伝承が記録されている。
おすすめの現代語訳
- 『日本書紀(現代語訳付き)』(講談社学術文庫): 詳細な注釈付きで、神話と歴史の関係がよく分かる。
- 『日本書紀 現代語訳』(中公文庫): 簡潔で分かりやすく、初心者にもおすすめ。
③ 風土記(ふどき)— 各地の神話と伝承
成立:奈良時代(713年)/地方ごとに編纂
特徴
- 奈良時代に各国(今の都道府県単位)ごとに作られた地誌。
- 地元の神話や伝説、地名の由来などが記録されている。
- 出雲国風土記は、日本神話と深い関わりを持つ。
おすすめの現代語訳
- 『出雲国風土記 現代語訳付き』(岩波文庫): 出雲神話を知るための必読書。
- 『風土記(現代語訳)』(ちくま学芸文庫): 各地の伝承を総合的に知ることができる。
2. 日本神話を体感する
神話の舞台を訪れる
日本神話をもっと深く知るには、実際に神話の舞台となった場所を訪れるのが一番です。
① 高千穂(宮崎県)— 天孫降臨の地
見どころ
- 天岩戸神社:天照大神が隠れた洞窟とされる場所。
- 天安河原:神々が集まり、天照大神を岩戸から出す相談をしたとされる場所。
- 高千穂峡:瓊瓊杵尊が降り立った地とされる神秘的な渓谷。
② 出雲大社(島根県)— 大国主命の聖地
見どころ
- 出雲大社: 大国主命を祀る神社。国譲り神話の舞台。
- 稲佐の浜:天の使者が大国主命と交渉した場所とされる海岸。
- 八重垣神社:須佐之男命と櫛名田比売が結ばれた場所。縁結びの聖地。
③ 伊勢神宮(三重県)— 天照大神の聖地
見どころ
- 内宮(ないくう): 天照大神を祀る日本最高の聖地。
- 外宮(げくう):豊受大神(とようけのおおかみ)、食物の神を祀る。
- おかげ横丁:江戸時代の参拝文化を体感できる町並み。
これらの場所を訪れることで、神話が単なる物語ではなく、「今も生き続けている伝承」であることを実感できます。
3. 日本神話と世界神話の比較
日本神話は、世界の他の神話と共通点を持っています。
① 天照大神とギリシャ神話のゼウス
- どちらも「最高神」であり、天界を統治する存在。
- 天照大神は「太陽神」、ゼウスも「雷を司る天の神」。
- 天岩戸神話(神が隠れ世界が暗くなる)は、ギリシャ神話の「デメテルとペルセポネ」の話に似ている。
② 須佐之男命と北欧神話のロキ
- どちらも「暴れ者の神」であり、時に秩序を乱す存在。
- ロキは北欧神話で最終的に神々と敵対、須佐之男命も高天原を追放される。
- しかしどちらも「英雄的な一面」も持ち、物語に欠かせないキャラクター。
③ イザナギ・イザナミと中国神話の伏羲・女媧
- どちらの神話も「男女の神が世界を創造する」ことが共通している。
- イザナミが死後、イザナギが後を追うが逃げ出す話は、ギリシャ神話の「オルフェウスとエウリュディケー」にも類似。
こうした比較を通じて、日本神話が「独自のもの」でありながら、世界の神話と共通する要素も持っていることがわかります。
4. 日本神話を学ぶためのおすすめ書籍
- 『日本神話の謎を解く』竹田恒泰(PHP新書): 初心者向け。日本神話の背景を分かりやすく解説。
- 『記紀神話の世界』吉田敦彦(講談社学術文庫):日本神話を世界神話と比較しながら考察。
- 『古事記と日本書紀—神話と歴史の間』斎藤英喜(ちくま学芸文庫):記紀の違いを学び、日本神話の成り立ちを探る。
エンディング
「日本創世の秘密」の物語は、これで一旦終わります。
しかし、日本神話の世界はまだまだ広がっており、今も語り継がれています。
「神々の物語は、今も私たちの暮らしの中に生きている。」
そう考えながら、日本神話の世界をもっと深く探っていってください。
「日本創世の秘密・番外編」完結!